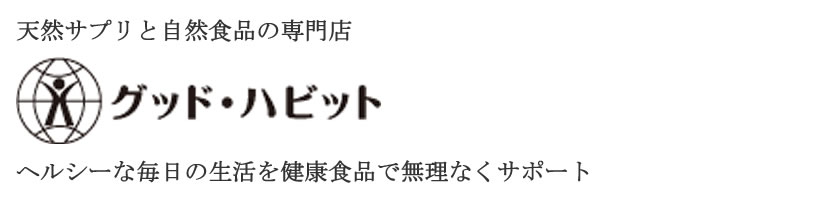東洋医学
証の概念
証(しょう) とは、東洋医学における診断の考え方の一つで、その人の体質や症状の全体像を総合的に判断するものです。
西洋医学では病名(例:風邪、胃炎など)を診断しますが、東洋医学では 「証」 によってその人の状態を見極め、治療法を決めます。
1. 証の構成要素
証は、主に以下の要素から構成されます。
① 虚証(きょしょう)・実証(じっしょう)
→ 体力やエネルギーの強さを判断する
・虚証(きょしょう):体力やエネルギーが不足している状態
・体が弱く疲れやすい
・声が小さい
・顔色が青白い
・食が細い
・寒がり
・例:慢性的な病気、冷え性、低血圧
・実証(じっしょう):エネルギーが充実しているが、過剰な部分もある状態
・体力がある
・声が大きい
・顔が赤みを帯びる
・食欲旺盛
・暑がり
・例:高血圧、炎症性疾患、便秘
・治療の方向性
・虚証 → 補う(「補法」:体力をつける、気血を補う)
・実証 → 減らす(「瀉法」:余分な熱や老廃物を取り除く)
② 寒証(かんしょう)・熱証(ねっしょう)
→ 体の冷え・熱の状態を判断する
・寒証(かんしょう):冷えが強く、エネルギーが低下した状態
・手足が冷たい
・顔色が白い
・寒がり
・便がゆるい(下痢しやすい)
・尿の量が多い・透明に近い
・例:冷え性、低血圧、甲状腺機能低下
・熱証(ねっしょう):熱がこもり、炎症などがある状態
・ほてりやすい
・のどが渇く
・便秘気味
・赤ら顔
・皮膚が赤く炎症を起こしやすい
・例:高血圧、発熱、湿疹
・治療の方向性
・寒証 → 体を温める(温補、温める食材や漢方を使う)
・熱証 → 熱を冷ます(清熱、炎症を抑える漢方や食材を使う)
③ 気・血・水(き・けつ・すい)の異常
→ 気(エネルギー)、血(血液)、水(体液)のバランスを診る
気(き)
・気虚(ききょ)(気の不足)
・疲れやすい、倦怠感
・息切れ、声が小さい
・風邪をひきやすい(免疫力低下)
・例:慢性疲労、胃腸虚弱
気滞(きたい)(気の流れが滞る)
・イライラしやすい、ストレスがたまりやすい
・胸やお腹が張る、げっぷが出やすい
・例:自律神経失調症、ストレス性の胃痛
血(けつ)
・血虚(けっきょ)(血の不足)
・顔色が青白い
・立ちくらみ、めまい
・皮膚が乾燥しやすい
・例:貧血、ドライスキン
・瘀血(おけつ)(血の流れが悪い)
・皮膚のくすみ
・シミ、肩こり、頭痛
・生理痛がひどい
・例:高血圧、冷え性
水(すい)
・水滞(すいたい)(水分代謝が悪い)
・むくみやすい
・めまい、耳鳴り
・下痢しやすい
・例:むくみ、アレルギー性鼻炎
・治療の方向性
・気虚・血虚 → 補う(補気・補血)
・気滞・瘀血・水滞 → 巡らせる(気を巡らせる、血流改善)
2. 証の組合せ(例)
証は単独ではなく、複数の要素が組み合わさることが多いです。
例えば、
・「気虚+寒証」 → 体力がなく、冷えやすい(慢性疲労・冷え性)
・「血虚+瘀血」 → 貧血気味で血流が悪い(冷え性・月経不順)
・「気滞+熱証」 → ストレスが多く、体に熱がこもる(イライラ・高血圧)
このように、証を総合的に判断して治療法を決めていきます。
3. 証の診断方法
証を判断するために、四診(ししん) という診察方法を用います。
① 望診(ぼうしん):顔色・舌の色・姿勢を見る
② 聞診(ぶんしん):声やにおいを聞く
③ 問診(もんしん):生活習慣や症状を聞く
④ 切診(せっしん):脈診(脈を診る)、腹診(お腹の硬さを診る)
4. 証に基づいた治療法
証に応じて、次のような治療を行います。
・虚証 → 体力を補う「補法」(漢方:補中益気湯など)
・実証 → 余分なものを取り除く「瀉法」(漢方:大黄・石膏など)
・寒証 → 温める(生姜・シナモン・附子など)
・熱証 → 冷やす(菊花・石膏・黄連など)
・気滞・瘀血・水滞 → 気血水を巡らせる(運動・マッサージ・針灸)
まとめ
証は 「体質+症状」 を総合的に診断し、バランスを整えることを目的としています。
自分の証を知ることで、適切な養生や治療法を選ぶことができ、より健康的な生活につながります。
広告
グッド・ハビット
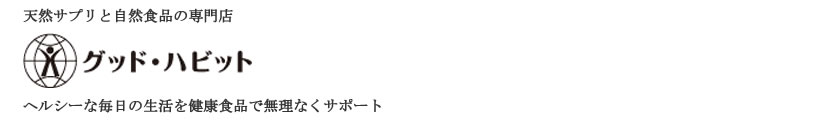
E-mail:goodhabit2020@gmail.com