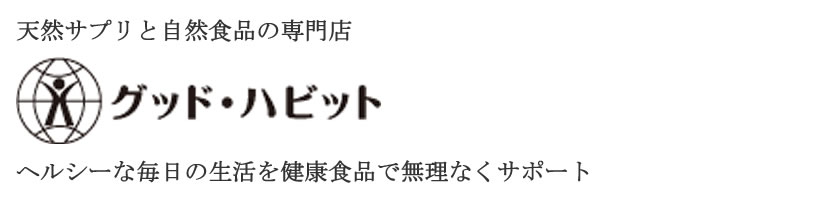東洋医学
東洋医学の考え方
東洋医学(伝統中国医学や漢方医学を含む)は、西洋医学とは異なるアプローチで人間の健康や病気を捉えます。その基本的な考え方を紹介します。
1. 全体観(ホリスティックな視点)
東洋医学では、身体を部分ごとに分けて考えるのではなく、「全体のバランス」を重視します。体だけでなく、
心や環境との関係も健康に影響を与えると考えます。
2. 陰陽(いんよう)のバランス
すべてのものは「陰」と「陽」の相対する2つの要素で成り立っており、健康もこのバランスが重要とされます。
・陰:冷たい、静的、暗い、夜、内側
・陽:熱い、動的、明るい、昼、外側
この陰陽のバランスが崩れると、病気になりやすいと考えられます。
3. 五行(ごぎょう)理論
五行(木・火・土・金・水)の5つの要素が、互いに影響し合いながら人体の機能や自然界を形成しているとする考え方です。
・木(肝・胆)→成長、伸びるエネルギー
・火(心・小腸)→活力、熱エネルギー
・土(脾・胃)→消化、栄養供給
・金(肺・大腸)→呼吸、免疫
・水(腎・膀胱)→生命力、成長・老化
五行のバランスを整えることで、健康を維持できると考えられます。
4. 気・血・水(き・けつ・すい)
人体のエネルギーと物質の流れを「気・血・水」の3つに分類します。
・気(き):生命エネルギー、活力
・血(けつ):血液や栄養の流れ
・水(すい):リンパや体液の流れ
これらの循環がスムーズであれば健康で、滞ると不調が生じるとされます。
5. 経絡(けいらく)とツボ(経穴)
人体には「経絡」と呼ばれるエネルギーの流れる道があり、その上に「経穴(ツボ)」が点在しているとされます。
・経絡の流れを整えることで、体の不調を改善できる
・鍼(はり)や灸(きゅう)、指圧などでツボを刺激し、治療を行う
6. 証(しょう)の概念
西洋医学の「病名」ではなく、東洋医学では「証(しょう)」という体質や状態の分類をします。
例:
・実証(じっしょう):体力があり、エネルギーが強すぎる状態
・虚証(きょしょう):エネルギーが不足し、体力が弱い状態
・寒証(かんしょう):冷えが原因の不調
・熱証(ねっしょう):熱がこもる不調
同じ病気でも、人によって治療法が異なるのが特徴です。
東洋医学の治療法
東洋医学では、以下のような方法で体のバランスを整えます。
・漢方薬(生薬を組み合わせた処方)
・鍼灸(しんきゅう)(ツボを刺激して気の流れを改善)
・推拿(すいな)・指圧(経絡に沿ったマッサージ)
・気功(きこう)・太極拳(気の流れを整える体操)
・食養生(体質に合った食事療法)
まとめ
東洋医学は 「バランスを整えること」 を最も重視し、体全体の調和を大切にします。
現代医学と併用することで、より効果的な健康管理が可能になります。
証の概念
証の概念については、こちらをクリック
広告
グッド・ハビット
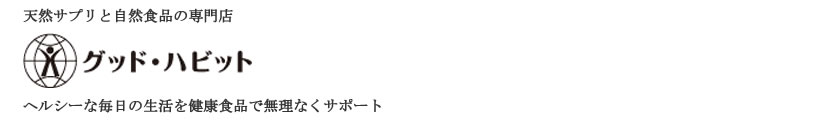
E-mail:goodhabit2020@gmail.com